


 |
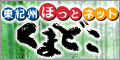 |
| 当サイトはどなたでもご自由にリンクしていただいて結構です。よろしければ上のバナーをお使いください。 |
|
 |
 |
楊枝薬師堂 <
ようじやくしどう > |
<
熊野市(旧熊野市、旧紀和町) > |
|
由来については、様々な話があるが、同薬師堂の傍らには次のような由来が記されている。
|

|

|
『楊枝薬師如来の来由は、京都三十三間堂棟木之霊地として、頭痛平癒、病脳療活に顕著なる霊場なり。
|
|
二条天皇の永暦年中の頃、先帝後白河上皇が頭痛の為再三お苦しみでした。上皇はおんみずから都の因幡堂にお籠りになり、平癒を祈願なさいました。
|

|

|
ある夜、金色の御仏が現れて「われは薬師如来である。熊野川のほとりに高さ数十丈の大楊樹あり、かの楊をきり都に大伽藍を建立し、かつ我が像を彫刻し、まつれば頭痛たちどころに、癒えよう」と。上皇は大変お喜びになり、早速その大楊を切らせましたが、あまりに長く大きいので、動かすことも出来ませんでした。困り果てていたところ、不思議や水中から天女現れ出て、神力で軽々と京まで運ぶことが出来ました。「柳のおりゅう」のことです。長寛二年、大伽藍を建立しました。今にいう蓮華王院即ち三十三間堂であります。ために上皇の頭痛は平癒しましたので上皇は歓喜して、熊野楊枝の郷の楊の切り跡にも七堂伽藍を建立され、上皇直作の薬師如来を本尊とあがめ、仁安二年九月十一日、法皇となられ自ら大導師となって開眼供養を、なされ頭痛山平癒寺と号されました。
|
|
その後度々火災に会いましたが、奇跡にも本尊薬師如来は今に残り、お祭りされています。悪事災難をまぬがれ、特に頭痛、平癒、来世は極楽浄土へお導き下さる。ありがたい薬師様であります。全国各地より今なお参詣の信者はあとを絶ちません。昭和五十年二月』
|

|
|
|
※熊野川のほとりにあり、春には梅や桜の名所として、観光にもよい。
|
 |
参考文献 |
| |
(境内紹介文より) |
 |
その他関連情報 |
| |
なし |
|