


 |
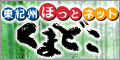 |
| 当サイトはどなたでもご自由にリンクしていただいて結構です。よろしければ上のバナーをお使いください。 |
|
 |
 |
稚子塚伝説 <
ちごづかでんせつ > |
<
御浜町 > |

|
うつろ舟にのってきたお姫さま
七里御浜海岸の中ほどにあった萩内という村で約200年前にあった出来事とされ伝承によると
当時この村に真水のわき出るところがあるので、地主の翁了(おうりょう)という人が、このわき水を利用して田を拓こうと、大勢の人を使って作業をしていた。
八つ刻(午後二時頃)となり、みんな浜辺に腰を下ろして休んでいると、一人の男が突然叫んだ。
「おい、あれは何だ。うつろ舟(空舟)が流れてくるぞ」
みんなが男の指さす方向を見ると、小舟が黒潮にのって、こちらのほうへ流れてきた。近づいてくる小舟を見ると、小舟の底に娘が伏せていた。
男たちは、我先にと海に飛び込み、舟にたどり着くと海岸へ引き上げ、ぐったりしている娘を助け出した。
娘は疲れ切っていたが、天から降りてきたような、それは美しいお姫さまであった。
地主の翁了は、すぐ姫を家に連れ帰り、手厚く介抱してやった。二、三日してようやく元気を取り戻したが、姫は自分の身の上を明かそうとはしなかった。
姫は阿波の国(徳島県)の大名の娘で、同国の乳ヶ崎海岸から、愛用の品々や金銀財宝を小舟に積み込んで流されてきたらしい、と風の便りで聞こえてきた。
|
姫は体の調子が良くなると、翁了に、
「お世話になりました。無理なお願いで申し訳ございませんが、近くの道端に小さな家を建てていただけませんか?日々の暇つぶしに、茶店でも開いて暮らしたいと思います。」
といった。
翁了は姫の申し出どおり、熊野三山参りでにぎわう街道沿いの、わき水の出る近くに家を建ててやった。姫はここに茶店を開き、草餅などを売って暮らした。
生まれついての美しさと心の優しい姫のことは、たちどころに近郷近在に広まった。
「わしの嫁になってくれぬか」
「息子の嫁になっておくれ」
数多くの申し入れがあり、新宮の殿さまも翁了に命じて城に入るように言ってきたが、姫は一向に応じるようすはなく、ついにはそんな話がこないようにと髪をおろしてしまった。
姫の茶店の下には、海岸には珍しくコンコンとわき出る清水があり、昔から、“起請の水”と呼ばれていたが、姫はこの清水に姿を映し、化粧や身づくろいをしたため、いつからか“化粧の水”と呼ばれるようになった。
|

|

|
姫は、元来が蒲柳(病弱)の身であったので、しだいに病に伏すことが多くなった。
姫は我が身の衰えを感じたのか、ある日、愛用の品をまわりの人々に配った。翁了には鏡と秘蔵の剣に巻物を添えて渡し、
「みなさん、大変お世話になりました。私はもう長くは生きることができません。私が死んだら、どうぞ七尾七里が見えるところに葬ってください。お世話になったご恩はけっして忘れることなく、村の人たちをお守りします。」
と話した。
しばらくして、姫は眠るがごとくに息を引き取った。村の人々は、遺言どおりに七尾七里を眺めることができる場所を探し、姫が住んでいたところから西方に五丁(約五百メートル)ほど離れた飛波山の頂上に遺体を葬り、冥福を祈った。
やがて人々はこの地を稚子塚と呼ぶようになり、“乙姫大明神”の碑を立てた。
四月三日の姫の命日には、今でも毎年盛大な祭礼が行われている。ここにお参りすると美人になるともいわれ、祭りの日は参詣する若い娘たちでにぎわっている。
|
 |
参考文献 |
| |
みえ東紀州の民話【三重県地域振興部地域振興課】 |
 |
その他関連情報 |
| |
なし |
|