


 |
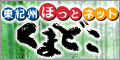 |
| 当サイトはどなたでもご自由にリンクしていただいて結構です。よろしければ上のバナーをお使いください。 |
|
 |
 |
平尾井薬師(細谷薬師) <
ひらおいやくし > |
<
紀宝町(旧紀宝町、旧鵜殿村) > |
|
圓通寺より東方約八丁(約800メートル)玉川の中程に昔冷泉が湧き出ていたと伝えられる、壷之井という清らかな水の淀みがある。薬師参詣者はここで口を漱ぎ、手を清めて、樹齢幾百年の杉檜や、樫の巨木が立ち並ぶ300余の石段を登りつめると、瑠璃色瓦葺朱塗木造建の荘厳華麗な堂宇が巨岩を背にして建っている。これが石尾山仏願寺の薬師堂である。石尾山仏願寺は石負山仏岩寺と称したこともある。
|

|

|
こらい、熊野へは歴代天皇が御幸されたとの記録があるが、白川法皇が寛治四年(1090年)以来十二回にわたって熊野三山に御幸され、このとき逢野細谷(相野谷)の地に薬師堂の建立を勅願して許されたのが、熊野三仏平尾井薬師であるとされている。本尊は、東方瑠璃光薬師如来であり、特に首より上の病気に霊験功徳ありと、近郷近在はもとより、遠方からの参詣者も多数ある。
|
|
御堂は幾度か炎上し、その都度建立した記録がある。寛永六年(1629年)、元禄六年(1693年)に記された薬師縁起に「薬師堂は古跡」とあり、建立願いについての記述が見られる。また「明治三年(1768年)薬師堂再建本寺圓通寺、平尾井庄屋佐七、棟梁九郎右衛門」と記された棟札が残されている。現在の建物は昭和三十八年に平尾井区民有志、篤志家の寄進により立て替えられたものである。
|

|

|
明治四十四年十二月一日付願出字不動地薬師堂を圓通寺仏堂に公認の件、大正元年十月二十五日付社第1355号を以って、三重県知事より公認されている。祭礼は毎年一月八日と、八月十六日の夜には昔より薬師踊りが奉祀され、夜の薬師の庭に昔をしのばせるこの神秘壮観な平尾井踊りは郷土芸能としても有名である。平尾井薬師周辺の老木の梅林は、薬師梅林として知られ、昔新宮藩からも薬師参詣と観梅に訪れ、参道口玉川壷之井横に乗物駕籠の据え場があったと伝えられる。
|
|
又、薬師堂の上の巨岩には足跡の肩が掘られているのが見られる。これは仏足跡と云われ、昔高貴な方が参詣の証として、刻まれたものであろう。
|

|
 |
参考文献 |
| |
「文化財を訪ねて」平成二年三月二十五日発行 紀宝町役場刊 |
 |
その他関連情報 |
| |
なし |
|