


 |
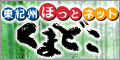 |
| 当サイトはどなたでもご自由にリンクしていただいて結構です。よろしければ上のバナーをお使いください。 |
|
 |
 |
幕末、命をかけて松本峠を越えた人 <
ばくまついのちをかけてまつもととうげをこえたひと > |
<
熊野市(旧熊野市、旧紀和町) > |

|
幕末、この地方にとって大事件である村替騒動があり、当事者の一人吉田庄太夫が熊野古道の1つ松本峠を感喜する民衆に担がれながら越えた史実を紹介します。
(写真:松本峠・木本側石畳)
|

|
安政の頃、新宮藩領主・水野忠央(ただなか)は政治的権力と金力をもって、本藩の紀州藩を抑え、実権を握ると幕府をも動かし多年の夢である村替を実施しようとした。
安政2年3月木本方面の27ヶ村(本藩の紀州藩領)と有田方面の5ヶ村(支藩の新宮領)との領地替が下知されるや、木本方面の村々があしかけ3年にわたり本藩の紀州藩から離れることに猛反対をし、いわゆる村替騒動になった。
(写真:吉田庄太夫画)
|

|
反対の理由は表向「歴代藩主の御恩忘れ難く、村替されるのは母から裂かれる子のようなもの」と終始一貫して共同目標をかかげ嘆願し、ひたすら基本姿勢を崩さず続けた。
本心は「新宮側の財、税政に対する不信や猜疑心(年貢の引上げ等)」であり「木本方面の27ヶ村は本藩に属するプライド(江戸時代の差別意識)」があったものと思われる。
(写真:木本神社)
|

|
あまりにも長く続く村々の抵抗に、江戸詰勘定組頭、吉田庄太夫が村替実施を命じられ安政4年5月11日江戸から木本へ説得にきた。
その日、木本では極楽寺の鐘が鳴り「庄太夫殿を突っ殺せ」と竹槍をとり大変な騒動であった。
庄太夫は侍と百姓という身分、階級を越え、人間と人間として命をかけて向き合い話しあった。
しかし説得にもかかわらず民意を動かす事が出来ないことを察し、庄太夫は藩命にそむき独断で「村替中止のことは身をもって引き受ける」と宣言し、有名な「村替据置」の誓紙を手交した。
(写真:木本神社内)
|

|
当時藩命にそむいた侍の責任の取りかたは、死をもって償う「自決」であった。
5月15日早朝「庄太夫、木本出立に文字どおり一期一会になることを察した人々は、その熱い血に触れようと代わるがわる庄太夫を担ぎ、前後に大明神幟(のぼり)をなびかせ泊峠(松本峠)を越え大泊まで見送った」とある。
庄太夫は江戸に戻り村替を中止させ、のちに江戸藩邸において自決した。
(写真:木本神社入口付近にある吉田大明神石碑)
|

|
私が松本峠を歩いていると「庄太夫を代わるがわる担ぎ大明神幟をなびかせ泊峠(松本峠)を越え・・・」を思い出し、担ぐ民衆は庄太夫が命をかけての決断であったことを知っていたのであろうか、また庄太夫はどのような思いで泊峠(松本峠)を民衆に担がれ越えたのかと思いめぐらせます。
のち吉田庄太夫は木本町の木本神社拝殿内に吉田大明神として祀られています。
(写真:松本峠・泊側)
|

|
お話を聞かせていただいた
熊野市大泊町
熊野古道語り部の
向井弘晏さん
|
 |
参考文献 |
| |
参考資料 熊野市史 |
 |
その他関連情報 |
| |
なし |
|